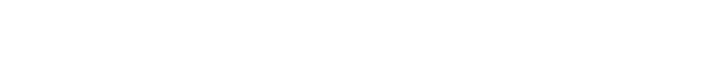一番高炉・二番高炉
1860年(安政7年)頃に手がけた高炉です。田鎖仲や田鎖源治らにより造られました。一番高炉と二番高炉は構造が異なり、一番高炉は石組みが四段積み重ねられ、上部には甘石に漆喰が塗られていました。内側には耐火煉瓦の炉が組み立てられており当時の高さは一番高炉が約7.8m、二番高炉は約7.9mでした。

三番高炉
仮高炉として大島高任の指導により、1858年(安政5年)に建設されました。その後、1864年(文久4年)頃に改修を行い、以降三番高炉として利用されました。一番高炉と二番高炉の廃炉後も稼働し、橋野高炉が廃止される1894年(明治27年)まで稼働しました。三番高炉の石組形式は、初期の高炉の基本形であったと考えられています。当時の高さは約7.0m。高炉中央には炉底塊があります。

写真提供:釜石市教育委員会

写真提供:釜石市教育委員会
山神社・市之助の墓山神碑
山神社は橋野高炉で働く作業員たちの安全祈願のために建立されました。高炉廃止となる1894年(明治27年)、御神体や手洗鉢などは橋野町中村の熊野神社へ移設されました。山神社の近くには、橋野高炉創業時に現地の管理者であった市之助が祀られている墓があります。

種焼窯・種砕水車場
種とは鉄鉱石のことです。高炉へと供給する鉄鉱石は、採掘された状態のままではなく加工されています。鉄鉱石を加工するための施設を種焼場と呼びます。人力のほか、水車の力で鉄鉱石を粉砕し、種焼窯で焼結。その後、金づちで砕いて高炉内に供給していました。

御日払所
事務所です。当時はその名の通り従業員の賃金支払いをはじめ、鉄鉱石や製品の管理もここで行われていました。
御日払所では橋野の川原で採集された餅鉄が買い取りされていたようです。その証拠として「餅鉄通」という台帳が残されています。
(餅鉄とは、河川に流され摩耗することで円礫状になった磁鉄鉱のことをいいます。古代製鉄において砂鉄と並ぶ重要な原料であり、橋野の川原で採集されていました。)