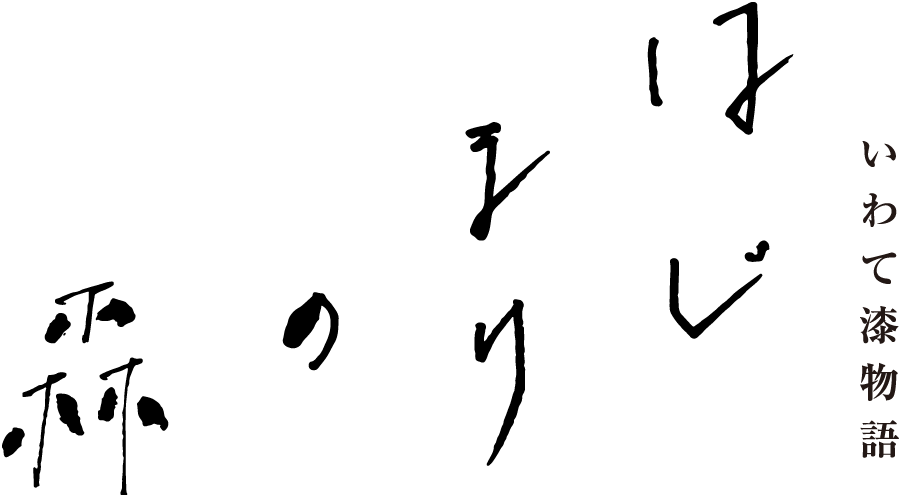6月から10月までは漆を掻き、11月から5月までは自分で採った漆で器をつくる。これが、漆かき職人であり、塗師でもある、鈴木健司さんの一年です。本来であれば、掻き手と塗り手は別であることが多く、浄法寺町でもどちらも手がける職人はほんの一握り。鈴木さんはその先達として、15年以上も、漆掻きと塗師の仕事を両立してきました。
「浄法寺漆は、薄く伸びて、カチッと硬い。扱いやすい漆なんです。でも同じ漆でも、職人の掻き方、考え方で品質が大きく変わります」。一年で20貫(約75kg)採れば一人前といわれますが、量だけでなく、上質な色とツヤを持った漆を採ることがとても大切。最盛期の8月をピークに、漆の木の状態や天候を見極めながら、10月上旬まで均一に採れるように調整していくのが難しいと話します。
鈴木さんが理想と考える漆は、飴色に透ける漆であり、歩留まりのいい漆。塗師であるからこそ、求められる漆がわかり、漆掻きだからこそ、木の育つ環境にまで目を配ることができる。両方の知識と技術を兼ね備えた鈴木さんですが、2つの道の奥深さは計り知れないとか。
「漆掻きも塗りも、思い通りにいくことは一度もありません。わからなければ先輩に教えを請い、自分なりに試行錯誤を重ねる。職人は死ぬまで勉強です」。そう話す鈴木さんも、職人の中ではまだ若手の域。しかしここ数年、ベテランが次々と引退するなど、危機感を募らせています。「漆を知り尽くした熟練者がほとんどいませんし、資源の問題も心配です。山主と連携して広範囲で漆の木を育てていかないと、いずれは枯渇してしまうでしょう」。目の前の状況に甘んじず、その先を見据えて努力することが必要ではないか…。今、鈴木さんはそんな風に考えています。

福島県出身。会津塗を学んだ後、本物の国産漆を使いたいという思いから、福島で漆を掻き、漆器を製作していた故・谷口史(つとむ)氏に師事。師匠の勧めもあり、日本うるし掻き技術保存会の研修を受けるため浄法寺へ。研修後、滴生舎の臨時職員として働いたのち、独立。夏場は漆掻き職人として山に入り、冬場は塗師として塗りに向き合う。